著作権あっても、自由に使える
自治体等が公開するオープンデータ
長野県の須坂市動物園で飼育されている鳥『トビの八兵衛』(下記写真)。名前からは想像できませんが、実はメスです。トビはオスメスの判別が難しい鳥で、名付けてしばらく経ったある日、卵を産んだことからメスだと判明。ただ、既に『八兵衛』として親しまれていたことから、現在もその名前のままだそうです。八兵衛を描いた下記のイラストは、飼育員が描いたもので、日頃から飼育、観察をしているからこそ分かる特徴が絶妙に描写されています。これらの写真やイラストは、須坂市動物園ウェブサイトのオープンデータのページに掲載されています。著作権は動物園にありますが、誰もが自由に使うことができ、再利用や再配布もできるデータと説明されています。どういうことでしょうか?
オープンデータは自治体等が公開しているデータで、著作権者の求める一定の条件を守ることで、誰もが自由に使え、加工、編集、再配布することもできます。また、読み取り、編集がし易いデータ形式で公開されているのも特徴です。実社会におけるデジタル技術の利活用について研究している工学部メディア工学科の兼松篤子講師は、「オープンデータには、自治体が共通して公開しているデータ(統計、防災、公共サービス等)と、その地域ならではのユニークなデータ(地場産業、観光、イベント等)があります。これらデータとデジタル技術の利活用によって、その地域にしかない魅力をアピールし、ブランド力を高め、強みを更に伸ばしていくことが重要です。官民の連携によって取り組むことが求められています」と話します。


CCBY須坂市動物園
自治体と企業・市民らによる『共創』がカギ
社会課題の解決や地域の発展へつなげよう!
オープンデータは、それ自体はweb上で公開された一つの情報でしかありません。それらを、地域が抱える課題の解決や、発展につなげるためにはどうすればよいのでしょうか。兼松講師は「市役所はもちろん、その関連施設、学校や企業、そして市民による『共創』がカギとなると考えています。地域の課題は何か、解決や発展に向け必要なデータは何か、どのようなデジタル技術が活用できるかなどを検討し、市民・企業・行政が協働で取り組むこと、共に新たな価値を創造することが重要です」と共創こそが地域振興の第一歩であると強調します。
デジタル庁はウェブサイトで、オープンデータ活用を検討する際の参考になるようにと、取り組み事例「オープンデータ100」を公開しています。
●税金が1日あたりどこにいくら使われているかを知る市民主導のプロジェクト
税金はどこへ行った?(Open Knowledge Foundation Japan)
<使用したオープンデータ> 予算情報、決算情報
<提供形態> Webアプリ
<これまでの課題> 税金の使われ方を知りたいと思っても、簡単に知る術がない。
<こう変わった> 税金が支える公共サービスの受益と負担の関係をわかりやすく理解できるようになった。
●共有しよう、「私の富士山」
富岳3776景(静岡県・山梨県)
<使用したオープンデータ> 富士山の写真、撮影位置情報
<提供形態> ブラウザアプリ
<これまでの課題> 世界に対してその魅力を発信する方法を模索
<こう変わった> 位置情報と連動することで隠れスポット・人気スポットが地図上でわかるようになった。
たくさんの富士山の画像データを、誰もが使用できるオープンデータとして発信
●ワタシだけの子育て支援ポータルサイト
かなざわ育なび.net(横浜市金沢区)
<使用したオープンデータ> 区内保育室一覧、医療機関一覧など
<提供形態> Webアプリ・スマートフォンアプリ
<これまでの課題> 子育てに関する多岐に渡る情報が行政のWebサイト内に分散し、検索性が悪い。
<こう変わった> 子どもの生年月日や郵便番号を入力すると、健康診断・予防接種の時期、保育園の空き状況など利用者に特化した情報を簡単に探せるようになった。
※上記は「オープンデータ100」(デジタル庁)を加工して作成
https://www.digital.go.jp/resources/data_case_study
地域社会を発展させる両輪
①DX推進+オープンデータ活用、②デジタル人材育成
冒頭の「トビの八兵衛」が飼育されている須坂市動物園は、多くの公立動物園がそうであるように、入園者の減少に伴う収益減、施設の老朽化、運営・維持管理など、多くの課題を抱えています。2016年からオープンデータの取り組みを始め、園内の動物の写真や飼育員が描いたイラストなどを公開し、ICTを用いた利活用につなげてきました。これらデータを活用した取り組みは、デジタル庁「オープンデータ100」でも紹介されています。兼松講師は2017- 2020年に須坂市オープンデータ推進会議の構成員を務め、これまで動物園が取り組んできたアナログの良さを残しつつ、新しい取り組みであるICTの利活用、その中でオープンデータを活用することで、アナログとデジタル、それぞれの良さを活かした相乗効果による、園の活性化を模索してきました。
その動物園を運営する須坂市と中京大学工学部、名古屋大学大学院情報学研究科、株式会社OpenFactory、GMOメイクショップ株式会社は「須坂市動物園におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に向けた連携協定」を今年9月に結びました。須坂市動物園のオープンデータ等の情報通信技術の積極的な活用によるDX推進および園の活性化事業、地域社会の発展に貢献することを目的としています。兼松講師は、「自治体におけるDX推進の実践的な取り組みは事例が少なく、動物園におけるDX推進はまだ国内で前例がないことから、この協定の意義は大きいと感じています。各機関が専門性を活かした役割を持ち、協働で取り組むことによって、動物園職員の働き方改革や収益構造改革へとつながることを期待しています」と意気込みを語ります。
また、兼松講師はデジタル人材の育成にも着目し、①DX推進+オープンデータ活用、②デジタル人材の育成が、地域社会を発展させるための重要な両輪と捉えています。「デジタル人材の育成は、学校に限らず、地域の各分野で学べる環境を構築し、興味関心をもつ子どもを地域で育てることが重要です。また、大人については、自分の専門と違う分野も幅広く学び、デジタルの力を活用して地域を盛り上げてほしいですね」と、地域が主体的に取り組むことに期待を込めます。デジタル庁も目指すべきデジタル社会の実現に向け、デジタル技術を理解し効果的に活用するためのスキルや能力である『デジタルリテラシーの向上』と、学校教育・リカレント教育等におけるプログラミング教育の充実による『デジタル専門人材の育成』など、デジタル人材の育成を推進しています。

プロフィール
金城学院大学大学院文学研究科社会学専攻博士課程を修了後、名古屋大学大学院情報学研究科特任助教を経て、2019年より現職。博士(社会学)。専門分野は社会情報学。
研究で心掛けていることは、地域の特徴、地域らしさをきちんと見ること。教育の場においても、地域について調べるだけでなく,実際に足を運び,現場の声に耳を傾け、利用者のことを考え、開発につなげるように学生を指導している。研究室にはキャッチコピー「情報技術の社会応用研究室」を掲げている。
兼松篤子講師
工学部メディア工学科


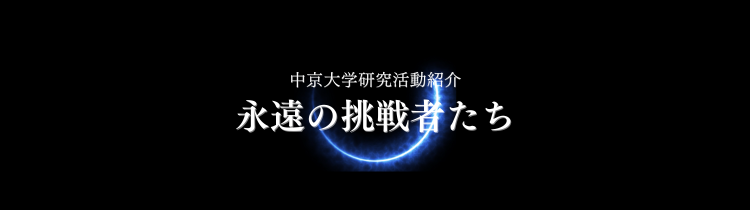

デジタル技術を活用した地域振興