サルは人間にとって馴染み深い存在
一方で厄介者扱いも(食物被害は7億円)
温泉に入り、気持ち良さそうにしているニホンザルの姿は、私たちの心を『ほっこり』とさせてくれます。長野県の地獄谷が有名ですが、温泉に入るのは子ザルと一部のメスだそうです。元々はそのような習慣はなく、餌付けされていた子ザルが温泉に落ちた餌を取ろうと入り、それがきっかけで他のサルも入るようになったと言われています。サルは「去る」の語呂合わせから、禍や不幸が去る縁起物、神様の使いとされてきました。また、「犬猿の仲」「猿も木から落ちる」などの慣用句、干支(9番目の申年)などにも用いられ、私たち人間と馴染み深い動物です。
一方で、厄介者扱いもされています。日本でのサルによる農作物被害は年間7億円に上り、シカ、イノシシに次いで第3位(2022年、農水省「全国の野生鳥獣による農作物被害状況」)。人馴れが進んだことで市街地や観光地にも度々出没し、被害も多数報告されています。サルの社会知能について研究をしている教養教育研究院の小川秀司教授は「一度、人里や街中で簡単に食べ物にありついてしまうと、その周辺がエサ場となります。一時的に追い払うことは可能ですが、再び来ないようにすることはとても困難です。被害の少ないうちに、防護柵の設置やエサ場を作らない(エサになる物を放置しない)、モンキードッグの活用などの対策を取ることを推奨します。また、地域や行政で、サルの生活環境を守ってあげることも忘れてはいけません」とサルとヒトとの共存について模索しています。
「サルは何を考え、どんな世界を見ているのだろうか?」
グルーミング(毛づくろい)、サルだんごで社会知能を発揮
「サルは何を考えているのだろうか?」「どんな世界を見ているのだろうか?」と問い続ける小川教授は、サルはどのような社会知能を持ち、それを日常生活でいかに発揮しているかを観察研究しています。「サルは相手の喜怒哀楽は分かるんですよね。でも、ヒトのように相手の知っていることや考えていることに思いを馳せることまではしていないようです。それなのに何故か、群れの仲間同士は上手く付き合っています」と興味深げに話します。「例えば、ニホンザルは、危険が近づくと群れの仲間に教えるために警戒音を発しますが、相手が既にその危険に気付いているか、まだ気付いていないかまでは考えることなく、教えようとしているようです」と、その無頓着な様子が滑稽で、見入ってしまったそうです。


●グルーミング(毛づくろい)
サルの社会行動の一つに、仲間同士で体毛に付いたシラミやその卵、ごみを取り除く毛づくろい(グルーミング)があります。仲の良さを示す行動で、親愛の挨拶、親密になるためのアプローチ、喧嘩の後の仲直りなど、群れの中で社会関係を築くのに役立っています。小川教授は「ネパールでアカゲザルを観察研究した時、こんな場面がありました。子供を産んだことのない若いメスが群れにいる赤ん坊を抱こうとしますが、母親から許しをもらえないでいます。その時、若いメスは母親にグルーミングをし始めました。親密さを深める行動が功を奏し、抱かせてもらえるようになったのです」と社会知能の一端を垣間見たと話します。また「タイでアッサムモンキーを観察研究した時です。メスとメスが喧嘩した後、負けた方が仲直りしようとグルーミングを試みますが、相手はまだ怒りが収まらなくて受け入れてくれません。すると、負けた方と仲良しのメスが、代わりに勝った方にグルーミングをしてあげ、2頭の仲直りの手助けをしたのです。本当に驚きました」と当時の様子を振り返ります。
●サルだんご
サルは寒さを凌ぐ時に、体を寄せ合い、おしくらまんじゅうのような状態で塊になります。これは「サルだんご」と呼ばれています。野生ニホンザルの場合、サルだんごは数頭くらいが主流ですが、瀬戸内海小豆島の銚子渓自然動物園お猿の国では数十頭以上になることもあり、毎年、ニュースで取り上げられます。
サルの観察研究をしてきた小川教授は「サルだんごは体温維持が目的で、小豆島では強いサルが真ん中の温かい場所に陣取るそうです。オス同士は競争関係にあることから、京都の嵐山モンキーパークいわたやまでは基本的には1つのだんご(塊)に入れるオスは1頭だけで,他はメスとその子供達です。メスの多くは血縁関係にある者同士になります」と話し、「一方で、中国の黄山に棲むチベットモンキーはオス同士も仲が良いので、オス同士でもくっつきます。ただ、交尾期はメスを巡る争いが強くなるため、メスと2頭のオスが三角形に位置して互いにくっつくことはあまりありません。弱い方のオスか、メスのいずれかが身を引くのでしょう」と続けます。オスとメスの関係、力関係など、サルだんごにはサル社会の縮図が見え隠れしているそうです。
サルによる被害対策に、モンキードック活用
「サル」と「イヌ」と「人々」の共存へ
農作物の味を覚えたサルの行動は、どんどん悪質化するといいます。山口県の「サル対策の手引き」によると、最初は特定の食物が被害にあい、そのうち、ほとんどの農作物にまで拡大するそうです。豊富なエサ場のおかげで栄養状態が良くなり、繁殖力が高まり、頭数が増加するとも説明しています。また、人馴れが進むと、家屋内の食べ物や人の持っている食べ物まで奪い始めると注意を呼び掛けています。対策として、エサ場を作らない、電気柵を設置する、モンキードッグ(訓練された猿追い犬)を活用することなどがあげられます。長野県大町市は鳥獣害対策として、全国で初めてモンキードッグを導入しました。その成果はすぐに表れ、常時40~50頭の群れで出没していたサルが導入後には激減し、追い払いを繰り返し行うことで、農作物被害もほとんどなくなったといいます。
小川教授は、「犬の放し飼いが許されている地域(日本は国の法律や都道府県の条例で規制)でこそ、モンキードッグによる農作物被害対策は有効です」と、サルの食物被害が大きく、費用がかかる対策を十分にとることができないアジア地域に目を向けています。現在、モンキードッグを活用した研究『アジア地域の農村と都市におけるサルとイヌと人々の共存』の準備を進めているそうです。「サルの生活環境、人々の生活環境、そこに多数いる放し飼いの犬や野良犬の存在。野良犬も訓練次第でモンキードッグのように働いてもらうことも可能かもしれない。農村と都市の両方でサルと野良犬と人々との三者の関係を調査し、モンキードッグを活用した三者の共存関係の構築を目指していきたい」と意気込みを語ります。
プロフィール
京都大学理学研究科博士後期課程修了後、京都大学霊長類研究所でのCOE研究員等を経て、1998年から中京大学へ、2020年より現職。担当科目は「生物学」「生物と環境」。
サルの研究を始めたきっかけは、言葉に苦手意識があり、言葉を持たない動物を研究対象に選んだこと。40年前から自転車旅行にはまり、世界各国を走っている。魅力は自分の力で遠くまで来たという充実感と、現地の人たちと道端で触れ合えるところ。言葉が通じないことも多いが、そこがまた面白い。動物研究も然り。
小川秀司教授
教養教育研究院


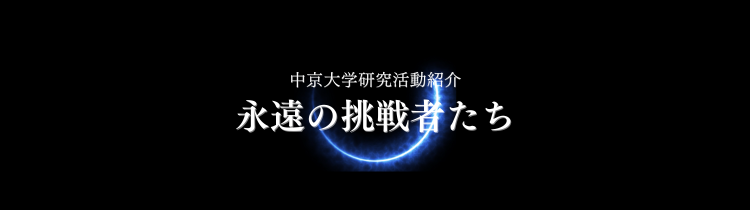

どんな世界を見ているのだろうか?