子どもたちの肥満や運動不足、体力低下は、解決しなければならない社会課題の一つです。しかし、家庭や子どもたちを取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。子どもたちの遊びも多様化していますし、昔ならどんな公園でもボール遊びができたり、子どもたちだけで気軽に外遊びができたりしていましたが、安全面等を考慮すると「今はそうはいかない」ということもたくさんあります。
スポーツ科学部の中野貴博教授は、子どもの運動・スポーツの促進、運動を通した成長の促進について研究を行っています。子どもたちが運動不足に陥るにはさまざまな要因が考えられますが、大人のとある思い込みを解消することが、大きなカギの一つになるようです。さて、そのカギとはいったい何なのでしょうか。
- ―――
- 運動不足だったり、肥満だったり。子どもたちの運動を取り巻く問題はいろいろ取り沙汰されていますが、実際のところどうなのでしょうか。
- 中野
- そうですね、体力はやはり落ちています。さまざまな要因がありますが、まずは子どもたちにとっての遊び自体が変わっていますよね。私の子ども時代は、遊ぶっていうと外で遊ぶぐらいしかなかったなあと(笑)。でも、今はそうじゃないですよね。よくゲームが運動不足の原因かのように思われがちですが、ゲームを産業としては否定できませんし、結局大人が与えているので、子どもたちだけを責めることはできません。
- ―――
- 遊びの選択肢が増えた分、外で遊ぶことを選ぶ機会も減ってくるという。
- 中野
- 運動やスポーツは今の子どもたちにとっては、教わってやるもの、という風になってきました。さらに、都心などでは、お金を払わないと体を動かす場所がない、なんてケースも少なくありません。
- ―――
- 私も子育て中なのですが、子どもに運動の機会を与えるって、いろんな意味でハードルが高いです。
- 中野
- 今はほとんどのご家庭がそうだと思います。僕が子どものころは親も「ちょっと外行っといで」という感じで、気軽に子どもたちだけで遊ばせていました。でも今はそうはいかないですよね。社会的にも環境的にも。これもゲーム同様、家庭だけの問題ではないと思っています。

- ―――
- 運動が得意ではないので、ルールやプレーを教えてあげなきゃと思うと、どうしても億劫に感じます。
- 中野
- それもよく保護者の方が陥る思考です。皆さん子どもから「サッカーやりたい」と言われたら、競技としてのサッカーを教えないといけない、と思ってしまいがちです。自分の子ども時代を振り返ってみてください。公園で近所のお兄ちゃんお姉ちゃんや友だちと、ボールを蹴ってサッカー風の遊びをしませんでしたか?
- ―――
- 確かに。人数もルールもちゃんとしたサッカーじゃないけれど、ボールを蹴って遊ぶことを、サッカーとして遊んでいました。正しいかどうかはわからないけれど、でもとっても楽しかった記憶があります。
- 中野
- ですよね。運動やスポーツと聞くと、大人はやっぱり競技のイメージを持っているという人が多いのです。スポーツ科学の分野でも、研究者の8割から9割は競技を専門とされているので、間違ってはいないのですが......。でも、子どもたちにとっては、必ずしも運動=競技ではありません。学校の体育の授業も今はだいぶ変わってきています。昔はいわゆる種目ベースで構成をされていましたが、種目じゃなくて、動きをベースに、遊びの延長線上のような形で行われています。

- ―――
- 体育の授業スタイルも変わってきたのですね。
- 中野
- 中野 ルールを理解し、種目がそこそこ楽しめるようになるのは小学校高学年ぐらいからなので、その頃までにはいろんな動きを経験している、という発想です。だから家庭でも「子どもに運動をさせよう」というと、野球チームに入れる、サッカーチームに入れるのではなくて、何でもいいから、いろんな体の動かし方を経験させてあげることの方が大事です。
- ―――
- となると、体の正しい動かし方を教えないと、と思ってしまいますが、もしかしてこれも......!?
- 中野
- はい、やめておきましょう(笑)。最初は下手なのは当たり前。でも、子どもたちは絶対に上達するので、完成形を大人が押しつけることはしない方が良いです。上手に遊べるようになった方がいいだろうと、つい教えたくなる気持ちもわかりますが「今はそんなのはいいんだ」と大人が割り切ることです。教えるよりも一緒にやってあげて、動きを見せてあげれば子どもたちは勝手にそれなりにできるようになります。
- ―――
- 子どもたち同士での外遊びには、体力面だけではない、子どもたちにとっていい成長の機会だそうですが。
- 中野
- 例えば、小学生同士で鬼ごっこをしているところに、誰かの幼稚園児の弟が来て「一緒に遊びたい」といわれたような経験、ありませんか。するとそのとき、「この子は小さいから、捕まっても鬼にはならないようにしよう」みたいなルールを作って遊びませんでしたか?
- ―――
- していました!小さな子も、お兄さんお姉さんも、その場にいるみんなが楽しむための特別ルールを、子ども同士で頭をひねって作っていました!
- 中野
- そういった経験を経て、思いやりだったり、チームコミュニケーションスキルだったりが磨かれていくんです。参加する全員が同じ土俵、同じルールでやらないと成り立たないっていう発想は、完成系を知っている大人の発想です。先ほどの、"正式なサッカーじゃないけどサッカーっぽい遊び"の話とも通じるのですが、競技としてやる野球は、3回ストライク取ったらバッター交代ですが、公園でやる野球って、バッターに打ちやすいよう近くから投げて、プレーする子どもによってはボールがバットに当たるまで打たせてあげるじゃないですか。私は、それで全然いいと思っています。
- ―――
- なるほどですね。子どもたちが運動を楽しむには、私たち大人側の意識改革が必要そうですね。
- 中野
- フィールドワーク等で、実際に保護者の方と話す機会もありますが、皆さん意外と自分の子どもが遊んでいる姿を見る機会って少ないと思います。近年共働き家庭も増えていますから。私たちが子ども向けの運動イベントなんかをやるときは、イベント開始前でも、とりあえず会場にボールを2,3個転がしておきます。すると、会場に着いた子どもたちは、特に何の指示をしなくても勝手にボールで遊び始めるんですよ。その様子を見て、保護者の方は「うちの子ってこんなにこんなに動くんだ!」と驚かれていますね。
子どもには体を動かす欲求があるので、「何かをさせてあげなきゃいけない」っていうより、「とりあえず外で思いっきり遊べる場所に連れてってあげよう」くらいで大丈夫です。 - ―――
- 子どもって、公園でたまたま会った知らない子と、いつのまにか仲良く遊んでいることがあります。親としてはうれしい反面、気を遣ってしまいます。仲良くできるかとか、初対面で遊ぼうなんて迷惑じゃないかとか......。
- 中野
- 私にも子どもがいるのでよくわかりますけど、子どもはそんなややこしいこと考えていません(笑)。もちろん性格の差はありますけど、多くの子が30分も経てば、知らない子ども同士で一緒になって遊んでいます。子ども同士の関わりって、ものすごい大きな成長のチャンスです。一緒に遊べる子ができたっていうことがまず大きな収穫だしスタートです。特に子どもたちが、ゲームなど他の楽しい遊びを覚える前に「体動かすの楽しいよ」と経験させてあげることが大切です。そういう機会を多く与えて、楽しみながら成長するっていうイメージです。大人も肩の力を抜いて考えられるといいですね。そしてせっかくなら、親子で一緒に走りまわるのもおすすめです。どうですか?これならできる気がしませんか。
- ―――
- できそうです!子どもたちに運動をさせるハードルがかなり低くなりました。運動=スポーツ、競技っていう思い込み、大人には結構根深くあるものかもしれないですね。
- 中野
- 繰り返しになりますが、競技としてちゃんとやらせてあげなきゃいけないっていうよりは、体を動かすことの楽しさや価値に気づかせてあげることが大人の役目なのかなと思います。対面でのコミュニケーションもそうですし、その場にいるメンバーが遊びやすいオリジナルルールを作り出すこともそうです。逆上がりができたとか、速く走れたとかももちろん立派なことなのですが、新しい友だちと仲良く遊んだことに保護者の方が気づけて、ほめてあげる。それも運動の重要な価値だということが、もっと社会に浸透するといいなと思います。
研究者プロフィール
筑波大学大学院体育科学研究科にて博士号(体育科学)を取得後、同研究科の研究員を務め、その後、名古屋学院大学人間健康学部(現。スポーツ健康学部)に赴任。同大学教授を経て2021年より現職。
主な研究テーマは、子どもの運動促進や体力向上、運動を通した子どもの育みおよび、運動の教育効果など。スポーツ庁の全国体力・運動能力、運動習慣等調査有識者委員会では長年、座長を務め、今年度からは愛知県においても子供の体力向上検討委員会の委員長を務める。その傍らで、日常的に学校や幼稚園、保育園、あるいは地域の現場に出向き、で子どもの運動指導、運動教室や体育授業の補助をゼミ生とともに行うことをライフワークとする。
※取材時時点
中野 貴博教授
スポーツ科学部


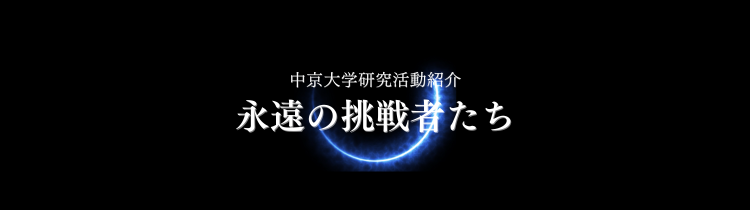

まずは運動=競技という思い込みを大人が捨てることから。