経営学部中村ゼミ 産学金連携授業最終発表
経営学部中村雅章ゼミとホンダカーズ東海、愛知銀行による産学金連携授業の最終発表が12月14日、中京大学名古屋キャンパスで行われた。
ホンダカーズ東海は、2018年から金融機関や高校、大学と連携し、産学金連携を推進して若者とクルマの接点を創出している。今年度は愛知銀行、中京大学と連携して経営学部の中村ゼミで産学金連携授業を行っており、学生たちが「未来の自動車ディーラーを考える」をテーマに、自動車販売の現状と課題を踏まえ、解決策を提案する企画書の作成に取り組んでいる。
 |
 |
| プレゼンテーションと質疑応答の様子 | |
この日行われた最終発表は、先日行われた中間発表のフィードバックをもとに学生たちがブラッシュアップして提出した企画の中から、ホンダカーズ東海と愛知銀行の担当者による事前審査で優秀企画に選出された5人がプレゼンテーションを行った。
審査の結果、最優秀賞に選出されたのは、2年生の古田莉子さんの企画「ディーラーで20歳を祝おう!」。経済的な面から若者がクルマを所有する機会が少なく、興味・関心がもてないという課題の解決策として、20歳の誕生日に家族がクルマを贈る文化を作ることを提案。若いうちからクルマを所有することで愛着と関心をもってもらい、将来の顧客として取り込むことを狙いとした企画案となっている。また、優秀賞にあたるホンダカーズ東海賞には、2年生の安藤鈴菜さんの企画「脱!運転恐怖症」が、同じく愛知銀行賞には、2年生の福本英伸さんの企画「未来の自動車社会に備えるB to B to Cプロジェクト」が選出された。
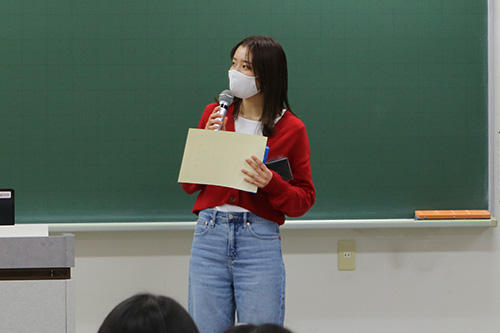 |
| 最優秀賞を受賞した古田莉子さん |
審査員を務めた愛知銀行執行役員法人営業部長の鈴木武裕さんは「皆さんのすばらしい発表に心から感動しました。なるほどと思うアイデアがいくつもあり、若い発想にはかなわないなと思いました。皆さんの今後の成長を楽しみにさせていただきたい」と賛辞を送った。
 |
| 中村ゼミ1~3年生とホンダカーズ東海、愛知銀行の方々で記念撮影 |
【受賞した学生のコメント】
■伝える技術
今回のプロジェクトから学んだことは、相手に伝える技術です。中間発表やゼミの授業で、ホンダカーズ東海さんや愛知銀行さん、そして中村先生からフィードバックをいただき、最終企画案を提出するまでに何度も修正を重ねてきました。この過程で、資料はわかりやすく、簡潔にまとめることがポイントであることがわかりました。伝わる資料を作成するには、図や色づかいを工夫し、文字は多くしすぎないことです。
しかし、中間発表で企業の方が言われた言葉が印象に残りました。「企画書を見るよりも、プレゼンを聞いた方がいいですね」という言葉です。企画書だけで本当に伝えたいことを100%伝えることは難しいということです。資料では伝えきれないことを伝えるために、プレゼン力も必要だと感じました。
企業の方に直接お会いしてお話をうかがうと、書面やZoomの画面とは違うものが得られます。プレゼンもそれと同じで、自分の熱意や本当に伝えたいことの伝わり具合は、話し方次第であるということも感じました。そこで、プレゼンでは資料を補足するように具体的な話をして相手の興味・関心を惹くように努めました。
今回のプロジェクトを通して、より相手に伝わる資料やプレゼンはどのようなものかを学ぶことができました。この経験を活かして、今後の活動も精一杯取り組んでいきたいです。
(経営学部2年 古田莉子)
■企画の背景を大切に
今回の企画を考える際に、最も重要視したことは現状のディーラーが抱える問題とその理由です。
問題点として、少子高齢化や若年層の車離れなどが挙げられます。そもそも車への興味や必要性がなければ自動車ディーラーに行くことはありません。都市部では公共交通機関が発達しているため、自動車を所有しなくても生活することができます。
そこで、免許をとってもペーパードライバーになる人が多いことに注目し、その人たちがもつ車への恐怖心を取り除き、運転の楽しさに気づき、車に興味を持つことができれば自動車ディーラーに行く人は増加すると考えました。そして、納車までの期間、そんな人たちの練習のため、何度も車を借りることができるという提案をしました。
「ペーパードライバーに重点を置く」という発想のヒントは、自分自身にありました。
私は免許を取得して間もない頃、親が大切にしている車を借りて大きな傷を付けてしまいました。この体験から、運転に対して恐怖心がうまれました。そして、その恐怖心は運転しない期間が長くなればなるほど大きくなっていきました。
このように、ディーラーの抱える問題である若年層の車離れに私自身が該当するからこそ、「なぜ?」のヒントを見つけることができ、今回の企画を提出することができたのだと思います。
このことを通じて、アイデア出しの際には相手が抱える問題とその理由は何かといった背景を大切にすることでヒントや解決策がうまれることを学ぶことができました。貴重な経験をさせていただいたホンダカーズ東海さん、愛知銀行さん、また中村先生に感謝の気持ちでいっぱいです。この経験を次につなげていきたいと思います。
(経営学部2年 安藤鈴菜)
■社会の未来を読む
5月中旬から始まった今回のプロジェクトでは、知識の浅い自動車業界についての提案ということもあり、はじめは皆苦戦していました。しかし、企業の方々や中村先生のお話、ゼミの時間に行った振り返り作業を通して、自分たちの提案の質を徐々に上げることができたと感じます。
私は現状の顧客の需要をできるだけ知りたいと考え、家庭内や友人間で、自動車はこうあってほしいなどの声を集め、それに対処できるような提案を考えていました。しかし、周りの人の意見だけでは偏りが出てしまううえに、未来の自動車ディーラーについて考えるというテーマとの整合性がとれないことに悩まされました。
その際、ホンダカーズ東海の方から、自動車のあり方は今、所有から利用へと大きく変動している、というお話をうかがい、まずはこの移り行く自動車社会の未来について考えることが先ではないかと考えました。自動車社会の未来像を考えることで、ディーラーに求められるものも、だんだんとみえてきました。
このプロジェクトを通して多くのことを学びました。特に、私は未来の自動車社会という時代を読むことで、そこに順応するための策がみえてくるというプロセスがとても心地よく、今後、他のプロジェクトにおいても、未来に続く時代の流れについてまず理解を深めることを心がけたいと思います。
今回、私たちのために貴重な場を設けてくださいましたホンダカーズ東海の皆さま、愛知銀行の皆さま、中村先生に感謝し、今後より一層精進していけるよう、ゼミのメンバーと一緒にがんばっていきます。
(経営学部2年 福本英伸)