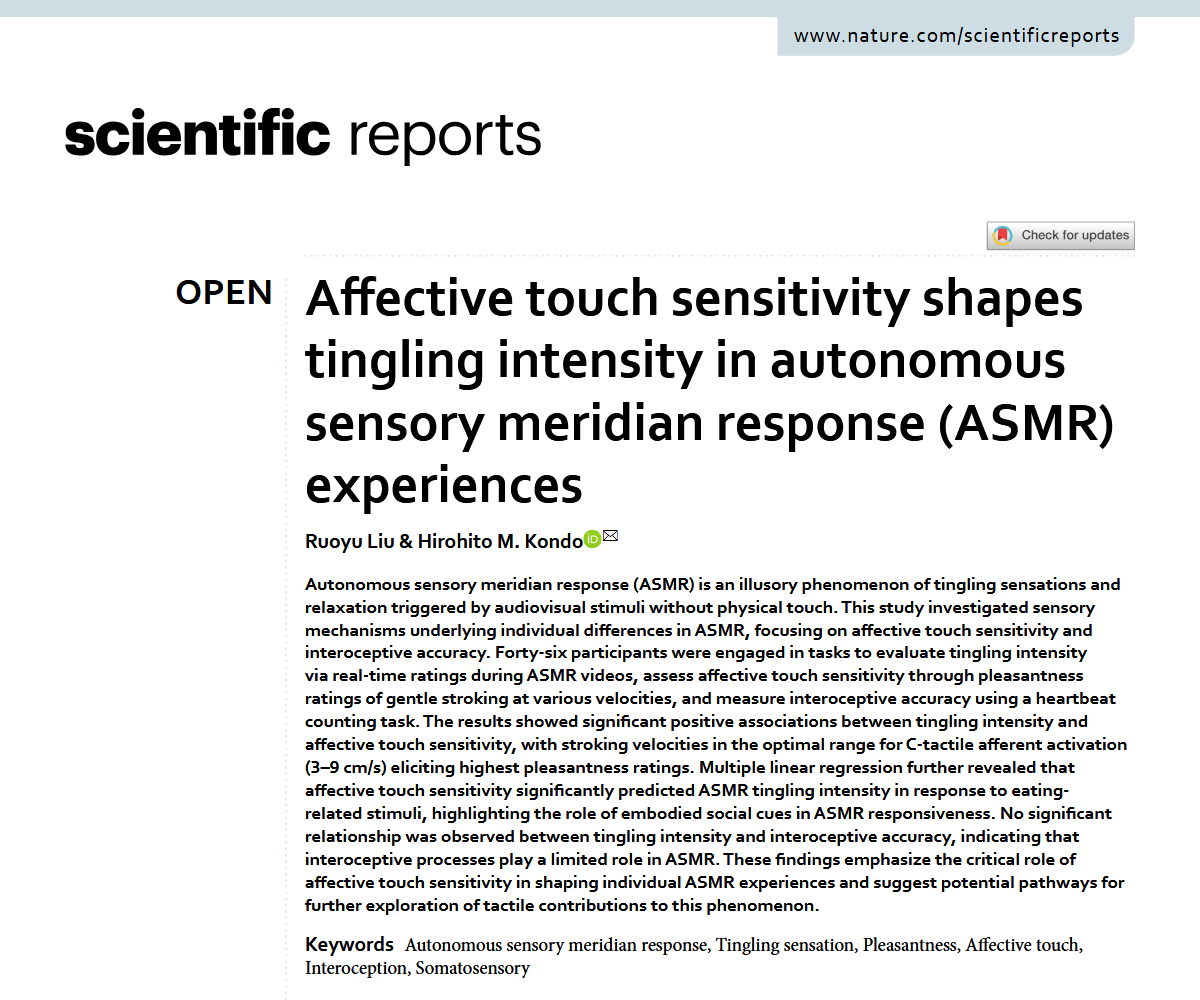心理学研究科/劉 若煜(リュウ ジャクイク)さん "Scientific Reports" 誌にて論文掲載
劉 若煜さん(心理学研究科 修士課程修了)と近藤洋史教授の共著論文が10月7日付で、学術誌 "Scientific Reports" にオンライン掲載されました。論文題目は "Affective touch sensitivity shapes tingling intensity in autonomous sensory meridian response (ASMR) experiences" です。
論文詳細はこちら
研究の背景
ASMR(自律感覚絶頂反応)は、囁き声やタッピングなどの音・映像によって「ゾクゾクする心地よい感覚」を引き起こす現象です。物理的な接触がなくても、触覚が生じる点が特徴です。しかし、この感覚を強く体験する人とそうでない人の違いは十分に解明されていません。本研究は、ASMRの個人差を生む要因として、「情緒的な触覚(affective touch)」と「内受容感度(interoceptive accuracy)」に注目しました。
目的
ASMRによるゾクゾク感の強さが、① 心地よいタッチへの敏感さ(情緒的な触覚)、あるいは② 自己の身体内部の感覚(内受容感度)と、どのように関係しているかを調べました。
方法
46名の参加者は以下の3つの課題をおこないました。
①ASMR課題 マイクへの接触音、近接音、咀嚼音、自然音などを含む動画を視聴し、リアルタイムでゾクゾク感の強さを評価しました。
②触覚課題 前腕あるいは手のひらをブラシで撫でられ、その心地よさを10段階で評価しました。C線維が最も反応する、ゆっくりした速度(3〜9 cm/s)での快情動が高い人ほど、「情緒的な触覚」の感受性が高いとされます。
③心拍数課題 自分の心拍を数えることで「内受容感度」を測定しました。
結果および考察
咀嚼音の動画において、ゾクゾク感の強さと情緒的な触覚との間に有意な正の相関が認められました。一方で、内受容感度とは有意な関係がありませんでした。この結果は、ASMR体験が「他者から触れられたとき、心地よさを感じやすいかどうか」に影響されることを示しています。ASMRは「音で感じる触覚」とも言える現象であり、その背後ではC線維による触覚処理が関与している可能性があります。とくに、咀嚼音のように社会的な文脈を伴う刺激で、この傾向が顕著だったことから、ASMRはデジタル空間において他者とのつながりや親密さを感覚的に再構築する現象とも考えられます。