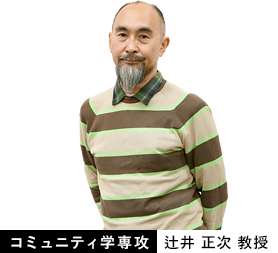幅広い人と関わる多様なプログラム
心理職の国家資格・公認心理師でもあり、発達臨床心理学を研究テーマとする辻井先生。現代社会学部の教授として学生たちを指導する一方で、研究者として、発達障害とその支援システムの開発や発達支援技法の開発などに取り組んでいます。長年にわたって国の施策にも携わってきました。また、発達障害を持つ子どもたちを支援する特定非営利活動法人の理事長を務め、積極的にサポート活動を行っています。
辻井先生のゼミは、学生たちも自閉症などの発達障害をもつ子どもたちと直に接したり、里親会との交流など、多様なプログラムがあります。プログラムを通じて、子どもだけでなく幅広い人と接することにもなります。こうした経験は、テキストを通して“知識”として得ていたものが“リアルにわかる”貴重な機会となり、学生自身が支援についてより多角的に、より深く考えるきっかけとなっていくようです。そんな辻井ゼミでは毎年、「発達障がい啓発週間」関連のイベントづくりにも携わっています。