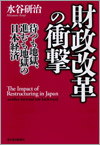幕末・維新期の八事山興正寺―八事文庫文書にみる尾張高野の明治維新―
中京大学経済学研究叢書第19輯
阿部 英樹(経済学部教授)著
八事山興正寺は、名古屋市内、屈指の名刹であり、かつての広大な境内の一部が中京大学の名古屋キャンパスになっている。本書は興正寺所蔵の八事文庫文書を紹介しながら、幕末から明治初年にかけての興正寺の動向にくわえて、「宝物」視されていた興正寺所蔵品の実態を明らかにしたものである。先に刊行した『江戸時代の八事山興正寺』の続編にあたる。
中京大学経済学部。2011年2月20日刊。462頁。